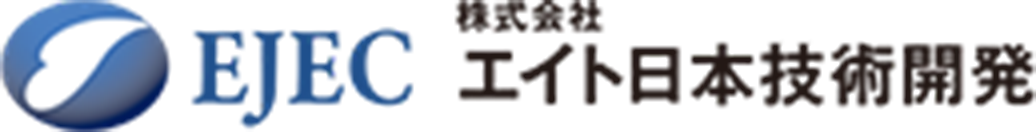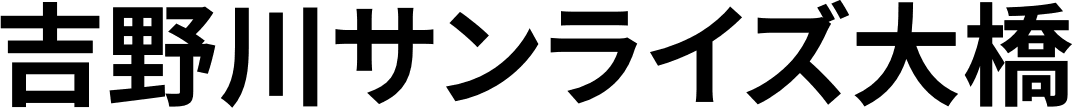吉野川大橋の耐震設計では、プレート境界型地震(タイプⅠ)と内陸直下型地震(タイプⅡ)に対する設計に加え、
発生が懸念される南海トラフ地震に対する検討を行い、巨大地震に対する耐震性能を確保しました。

吉野川大橋の基礎設計では、厚く堆積した軟弱地盤の地盤特性に応じて、
液状化、地震波、橋と地盤の共振に配慮した基礎構造を検討しました。
調査結果に基づき、液状化の影響を受けないよう、河川構造令に基づき鋼管基礎天端を既往最深河床から2m以上確保 。
また、地盤特性に応じた地震波により耐震設計を実施し耐震性能を確保しました。
【設計のポイント】
構造形式を設計するにあたり、共振を避ける目的で免震設計は採用せず、長周期化を避けた剛結構造を採用しました。


橋全体を15径間連続箱桁形式とすることで、ジョイントを橋台部の2カ所のみとしました。
これにより、耐震性能、耐久性、景観性、走行性、維持管理性能の向上を図りました。
連続化することで、地震時に桁が脱落する恐れがなくなるほか、
ジョイントからの漏水によるコンクリートの劣化・汚れ防止にも貢献します。
ジョイントがなくなることで、段差による走行時の騒音も低減されます。
【設計のポイント】
橋長が長いことから、大規模な伸縮量に対応するため、支承の施工にポストスライド方式を採用し、連続化を実現しました。



P4橋脚~P9橋脚で、上下部工剛結構造を採用し、経済性、耐震性能、維持管理の向上を図りました。
また、共振を避けることができる剛結構造を採用するにあたり、液状化、地盤特性を考慮した設計を行うことで、
巨大地震に対する耐震性能を向上させました。
【設計のポイント】
支承が構造上や維持管理上の弱点となることを考慮し、可能な限り剛結構造を採用することで、
支承コストの縮減による経済性の向上や不静定構造による耐震性の向上が図れ、支承数削減による維持管理性の向上にも寄与しました。
連続ラーメン化の対策として、「水平反力調整工法+後施工ラーメン化工法」による橋脚断面力を軽減。
これにより、剛結基数と固定支間長を増加させることができました。