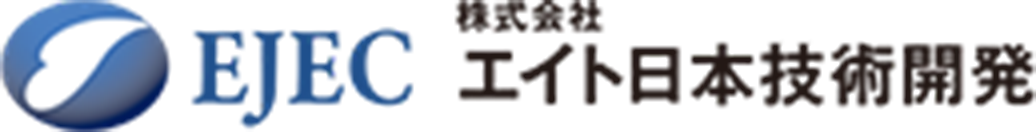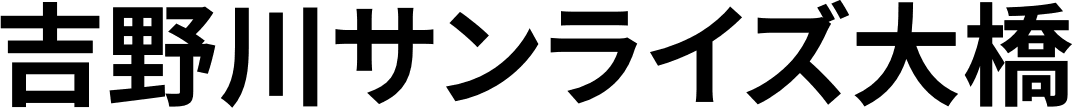架橋位置は、河口域に位置することから、各下部工への資機材の運搬はすべて船(台船、作業船、交通船等)による移動となります。
吉野川河口域は自然のゆらぎによる地形変化も激しく、船の喫水確保のため、河床浚渫が必要でした。
また、現場は波浪および強風の影響を受けやすく稼働率が低い厳しい環境下であったため、浚渫作業には多くの期間を要しました。





河川内橋脚の基礎形式は、鋼管矢板井筒基礎を採用していました。
円を描くように、全長約60mの鋼管矢板を1基につき34~40本を並べて打設します。
鋼管矢板打設後、円形の井筒内を掘削した後に、水を抜き、橋脚を構築しました。


本橋の上部工は、工期短縮を目的として、プレキャストセグメント工法を採用しました。
その他、プレキャストセグメント工法の適用により、工期短縮以外のメリットとして、
コンクリートの品質向上、河川内への汚濁水漏出の低減、架設作業の簡素化などが挙げられます。
セグメント製作は、架橋位置周辺の2箇所の製作ヤードで行いました。
両製作ヤードともに埋立地であるため地盤が軟弱ということもあり、
沈下対策の最小化かつ敷地面積の制約の観点から「ショートラインマッチキャスト方式」を採用しました。



本橋の河口部は浚渫量を最小限として環境負荷を軽減するため、河川内の支間長をすべて130mとしました。
上部工の架設方法は、平面線形が比較的に直線に近く、水深が浅いP5~P12橋脚までは架設桁による架設、
平面の曲率半径が小さく水深が深いP1~P4橋脚までは、エレクションノーズと台船による架設を採用していました。

補助桁併用張出架設(河川上空から補助桁による資材搬入)
右岸側、浅瀬の直線区間で採用(P5-P12)

エレクションノーズによる張出架設(海上から台船による資材搬入)
左岸側、水深が深い曲線区間で採用(P1-P4)